無料相談 24時間受付中
03-5579-9973
建設業における一人親方とは?個人事業主との違い
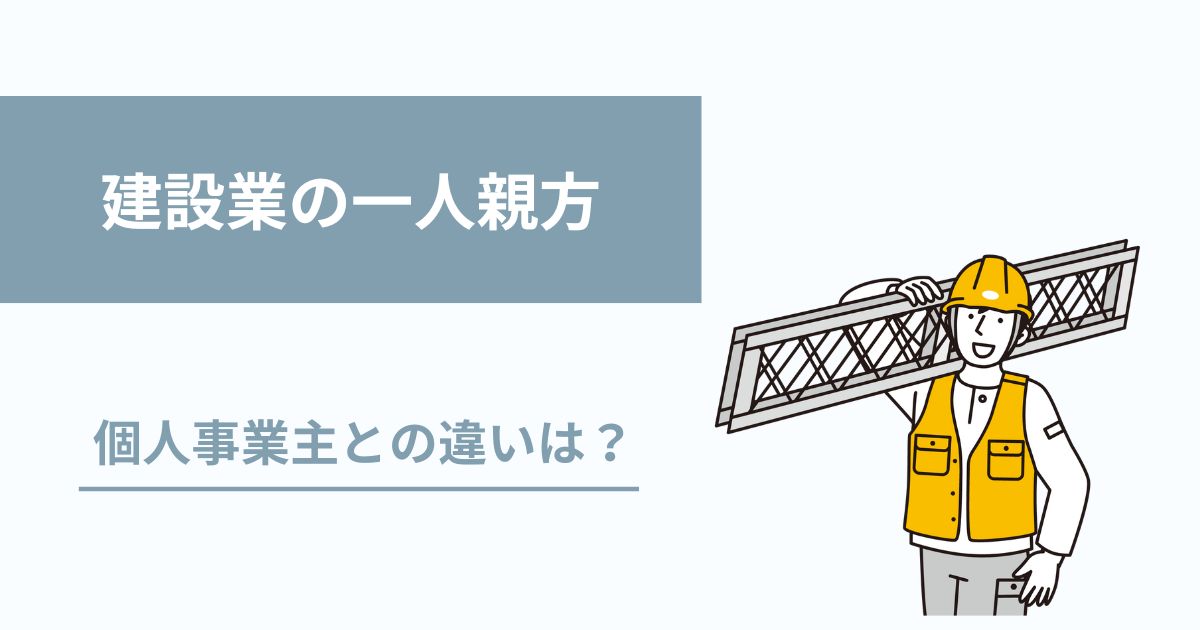
建設業で働く一人親方とは、個人事業主として独立し、自由に請負契約を結ぶ職人の働き方を指します。
現場で働く職人の中には、会社に所属せず個人で請負契約を結びながら働ける「一人親方」のスタイルを選ぶ人が少なくありません。
自由な働き方や報酬の調整がしやすい点も一人親方を選ぶ理由のひとつです。
しかし、一人親方になるには元請業者との関係や保険制度への対応など、制度的な理解も求められます。
今回は一人親方とは何かをテーマにして、その基本的な定義から働き方の特徴、メリット・デメリット、そして知っておきたい制度までを、初めての方にもわかりやすく解説していきます。
一人親方とは?
建設業界では「一人親方」という言葉をよく耳にします。
しかし、一人親方というイメージはわかるけどはっきりとした定義がわからずに使われていることも多いのが現状です。
建設業者は適正に現場を回すためにも、一人親方の正しい知識を持つ必要があります。
ここでは一人親方に関する基本的知識を解説していきます。
建設業界で使われる「一人親方」の意味
一人親方の正式な法的定義はありませんが、一般的には「従業員を雇わず元請業者などから直接仕事を請け負って現場で作業する個人事業主」のことをいいます。
自分の技術や経験を活かして自由に仕事を受けられるのが特徴です。
ただし、会社に所属していないため、労働基準法や労災保険といった労働者向けの制度の対象外になることが多く、自身で安全対策や保険加入の対応をする必要があります。
また、元請との契約書作成や安全書類の提出など、仕事の進め方も通常の労働者とは異なる点に注意が必要です。
一人親方が多い業種
建設業において一人親方が多い業種には、「とび工」「大工」「内装仕上工」「電気工事」「塗装工」などがあります。
これらの業種に共通するのは、高度な技能や専門的な経験を持つ職人が多く、個人でも一定の工事を請け負える点です。
特にとび職や大工などは、道具や機材を自前でそろえれば一人でも現場作業が可能です。
長年の現場経験や人脈を活かして元請から直接仕事を受注するケースも多くなります。
一人親方の多い業種では、個人の裁量や専門性が生きる職種が中心となっており、自立した働き方が成立しやすい環境にあるといえます。
一人親方の働き方と特徴
一人親方の働き方は、会社に雇われるのではなく、個人で請負契約を結び、自らの責任で建設現場の作業をするスタイルです。
元請業者や工務店などから直接仕事を受け、自分のスケジュールや仕事量を調整しながら働けるのが大きな特徴です。
収入は自分の働き方や実績に応じて変動しますが、成果がそのまま報酬につながるため、やりがいを感じやすいというメリットもあります。
一方で、会社員のように労災保険や健康保険に自動的に加入しているわけではないため、自分でそれらの手続きをしなければなりません。
また、帳簿の記帳や確定申告、安全書類の提出など、事務作業もすべて自分で対応しなければなりません。
このように一人親方は、現場作業に加えて経営者的な側面も持ち合わせている点が特徴であり、技術力と自己管理能力の両方が求められる働き方です。
一人親方と個人事業主の違い
一人親方と個人事業主の違いはわかりづらく、同じ意味として使われている場合も少なくありません。
実際、現場においては一人親方と呼ばれることがほとんどであり、契約の方法や労災保険の取扱いに悩む元請業者の多いのが現実です。
建設業において、両者にどのような違いがあるのでしょうか。
具体的にその定義を説明していきます。
働き方と契約形態の違い
一般的には「一人親方」と「個人事業主」はどちらも会社に雇われない自営業者という点では共通していますが、働き方と契約形態に違いがあります。
建設業においては労働者を雇わない個人事業主が一人親方であり、広義の意味では同じです。
一人親方は元請業者などから直接現場の作業を請負契約で受け、実際に作業員として現場に出る職人のことをいいます。
対して個人事業主は、法人化せずに自ら事業を営む経営者であり、自社の労働者や下請業者を使って工事全体を管理したり、経理や営業なども行う立場です。
また、一人親方が締結する契約は、基本的に自らの作業に対する報酬を得るための単独請負契約が中心です。
つまり、一人親方は現場作業の担い手であるのに対し、個人事業主は事業全体を運営する責任者ともいえます。
税金や社会保険の取り扱いの違い
社会保険については、基本的にどちらも厚生年金や健康保険に加入する義務はなく、原則として国民健康保険と国民年金に加入します。
しかし、労災保険や確定申告については注意が必要です。
次にその仕組みを解説していきます。
労災保険の加入義務
一人親方と個人事業主の大きな違いのひとつが、労災保険の取り扱いについてです。
ここでいう個人事業主とは、建設業以外の一般的な業種の場合も含みます。
労災保険は本来、労働者を対象とした制度であり、一般的な業種の個人事業主は労働者を雇った時点で労災保険の加入義務が生じます。
ただし、個人事業主本人は労働者でありませんので、民間保険等の加入を検討する必要があります。
しかし建設業などの危険を伴う業種では、一定の条件を満たせば「特別加入制度」により個人事業主でも加入ができます。
一人親方は労働者を雇いませんので、労災保険の加入義務はありません。
確定申告
一人親方と個人事業主はどちらも自分で所得を申告し納税する必要がありますが、確定申告の方法や扱いにはいくつかの違いがあります。
個人事業主は、開業届を税務署に提出して事業を開始します。
青色申告申請をすれば、最大65万円の控除や赤字の繰越、給与の必要経費化など、さまざまな税制上のメリットを受けられます。
これに対し、一人親方の中には開業届を提出せず、白色申告で確定申告している人も少なくありません。
白色申告は帳簿の作成が簡易で手軽な反面、青色申告のような特典が受けられず節税面で不利になることもあります。
また、個人事業主は帳簿づけや経理処理をするなど事業者としての自覚を持って申告する傾向があります.
一方、一人親方は現場の職人という意識が強く、確定申告は最低限にとどめているケースもあります。
一人親方のメリット・デメリット
建設業界において、現場作業を担う一人親方の存在は大きいものです。
高い技術力と豊富な経験をもっている一人親方は、元請業者にとっても助かる存在です。
実際、全建設業就業者の約10〜15%が一人親方と推定されます。
つまり、建設業就業者が約500万人とすると、約50万〜75万人が一人親方です。
この数は一人親方で働くメリットの大きさが影響しているといえます。
メリット
一人親方として働くにはメリットがたくさんあります。
- 自由度が高い
- 独立が簡単
- コスパがよい
その利点を大きく活かすことで安定した業務を継続させることも可能です。
ではどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
自由度が高い
一人親方として働く最大のメリットの一つが「自由度の高さ」です。
会社に雇用されているわけではないため、働く時間や仕事の内容、受注先を自分で選べます。
例えば、繁忙期に多く働いて収入を増やし、閑散期には休みを取るといった調整も可能です。
また、複数の元請業者と取引することもできるため、特定の企業に依存せずに働けるのも大きな利点です。
さらに、仕事の進め方や作業のペースも自分の裁量で決められるため、自分のスタイルを大切にしながら働けます。
技術や経験に応じて報酬交渉ができる点も、一人親方ならではの魅力です。
特に熟練した職人であれば、評価されやすく、案件ごとに高い報酬を得るチャンスもあります。
独立が簡単
一人親方は独立のハードルが低いといわれています。
建設業界では、特別な資格や大規模な資本がなくても、自分の技能と道具があれば現場で働けるので、比較的簡単に独立開業が可能です。
特に長年現場で経験を積んできた職人にとっては、既に仕事の流れや人脈があるため、元請業者から直接仕事を受けて一人で現場に入ることもスムーズに始められます。
また、法人を設立する必要もなく、税務署に「開業届」を提出すれば個人事業主としての手続きも比較的簡単に済ませられます。
必要な設備や資材も、最小限の初期投資でスタートできる場合が多く、リスクを抑えて自立した働き方を選べるのです。
こうした手軽さから、職人としての技術とやる気があれば、比較的早い段階で独立を実現できる点が、一人親方という働き方の大きな魅力といえるでしょう。
コスパがよい
一人親方のメリットとして注目されるのが、コストパフォーマンスの良さです。
会社を設立したり従業員を雇ったりする場合には、人件費や社会保険料、事務所の家賃など多くの経費がかかります。
しかし一人親方は、基本的に自分一人で現場作業をするため、こうした固定費を大幅に抑えられます。
また、売上がそのまま自分の収入に直結しやすく、努力や実績次第で効率的に収益を上げることが可能です。
確定申告で経費計上できる範囲も広く、仕事に関する交通費・工具代・作業着などを経費として処理できれば、税負担を軽減しつつ手取りを増やすこともできます。
さらに、法人と違って税務や社会保険の手続きも簡略化されており、会計ソフトを使えば自力で処理することも現実的です。
このように、一人親方は少ない初期投資で始められ、経費を抑えながら高い収益性を確保できる、非常にコストパフォーマンスの高い働き方といえます。
デメリット
一人親方は自由度が高い一方で、現場作業から経理事務まで全てを一人で行わなくてはなりません。
そのため、非常に多忙な毎日となり、時間に余裕がなくなるなどの面もあります。
次に一人親方の抱える問題点についてみていきましょう。
- 自己責任
- 契約のトラブル
- 仕事の安定性に不安
自己責任
一人親方として働くうえで大きなデメリットとなるのが、すべてが自己責任であるという点です。
仕事の受注、契約、現場での安全管理、作業品質、スケジュール管理、さらには税務や保険の手続きに至るまで、すべてを自分ひとりでこなさなければなりません。
現場でケガをした場合でも、あらかじめ特別加入制度を利用して労災保険に加入していないと、公的な補償を受けられないリスクもあります。
また、仕事が途切れた場合の収入補償はなく、営業活動を怠ればすぐに収入がゼロになる可能性もあるのです。
つまり、一人親方は自由度が高い反面、何かトラブルがあってもすべて自分で責任を負う必要があるのです。
それに対する準備や心構えが求められるのです。
契約のトラブル
一人親方として働く際に注意すべきデメリットの一つが、契約に関するトラブルのリスクが高いことです。
一人親方は、元請業者などと直接仕事の契約を結ぶ立場にあります。
その契約が口頭のみであったり内容が曖昧であったりすると、後々トラブルになる可能性があります。
「報酬の支払いが遅れる」「追加作業を無償で求められる」「作業の範囲をめぐって揉める」といった問題が発生しがちです。
また、立場的に元請からの力関係が強く不利な条件でも断りにくいケースもあります。
一人親方は、基本的に自ら契約書の内容を確認し必要に応じて文書化するなどの対策が必要です。
仕事の安定性に不安
一人親方には仕事の安定性に対する不安があります。
毎月の固定給やボーナスが保障されているわけではなく、受注状況によって収入が大きく変動します。
繁忙期にまとめて稼げる反面、閑散期になると仕事が途切れ、収入がゼロになるリスクもあります。
加えて、元請業者や工務店の都合で契約が突然キャンセルされたり、予算・工期が短縮されたりすることもあります。
急に収入が減少するケースも少なくありません。
こうした不確定要素が重なると、生活費や保険料、税金などの支払いが滞る恐れがあり、精神的なストレスも大きくなります。
結果として、安定的な収入を確保するためには、常に次の仕事を探し続けたり、複数の取引先と関係を維持したりする努力が不可欠となるのです。
一人親方になるには?必要な手続き
建設業界で経験を積んだ職人が「一人親方」として独立するケースは珍しくありません。
しかし、ただ「独立したい」と思っても、具体的に何から始めればよいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
一人親方になるには、開業届を出すのが主流です。
また、元請業者や下請業者との契約実務、万が一の事故に備えるための特別加入なども知っておく必要があります。
開業届を提出する場合
まずは職人として十分な技能・経験を積んだうえで、税務署へ「個人事業の開業届」を提出します。
青色申告のメリットを受けたい場合は同時に「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記による帳簿づけを始めましょう。
続いて、建設業で案件を請け負うために工事金額や件数に応じて建設業許可の申請も可能です。
労災保険は特別加入制度を利用し、労働保険事務組合を通じて申請・保険料納付すれば、ケガや事故の補償が受けられます。
開業届を提出しない場合
現場経験を活かし、開業届を提出せず一人親方として仕事を始めることも可能です。
この場合、報酬は源泉徴収なしで受け取り、所得税は確定申告の際に「事業所得」として申告します。
青色申告控除は受けられませんが、簡易帳簿で済むため負担は軽減されます。
建設業許可が必要な工事規模を超える場合は、許可申請も行えます。
白色申告では貸借対照表などがありませんので、自分で財務諸表を作る必要があります。
また「特別加入制度」で労災補償を確保し、現金出納帳や領収書を整備することで、後日の税務調査やトラブルに備えられます。
徐々に事業規模が拡大したら、開業届・青色申告への移行を検討しましょう。
その他の必要な手続き
一人親方として建設現場で働く際、元請・下請との契約実務には十分な注意が必要です。
口約束ではなく、できる限り書面による契約を交わすことです。
契約書がない場合、万が一のトラブル時に報酬や業務範囲の確認ができず、不利な立場に立たされることがあります。
契約前には業務内容、報酬、支払時期、損害責任の範囲などを明確にし、納得したうえで業務を始めるようにしましょう。
また、一人親方として労災保険特別加入の手続きも早いうちから検討しましょう。
一人親方に関するよくある質問
建設業で一人親方として働くにあたり、多くの方がさまざまな疑問や不安を抱えています。
特に初めて独立する方にとっては、制度の複雑さや契約上の注意点など、知っておくべきポイントが多くあります。
ここでは、一人親方に関するよくある質問を解説していきます。
- 一人親方で独立するときに助成金はもらえる?
-
一人親方として独立する際にも、条件を満たせば国や自治体が実施する各種助成金・補助金を活用できます。
代表的なのが「小規模事業者持続化補助金」で、商工会議所や商工会を通じて販路開拓費用などの一部を支援(上限50万円程度)してもらえます。
また、都道府県・市区町村が創業支援として独自に設ける助成金制度もあり、開業費用や研修費などの補助を受けられる場合があります。
まずは最寄りの商工会議所や自治体窓口に相談し、自身の業種や資金使途に適した制度を確認したうえで申請手続きを進めましょう。
- 一人親方でも融資は受けられる?
-
一人親方でも、事業運転資金や設備投資のための融資を受けることは十分可能です。
まず、信用金庫や地方銀行は「個人事業主向け融資」を用意しており、法人ではなくても事業計画書や過去数期分の確定申告書、収支予測などを提出すれば審査を受けられます。
また、国の制度を活用する方法として、日本政策金融公庫の「新創業融資制度」などがあり、無担保・無保証人での融資も一定条件下で可能です。
さらに、信用保証協会の保証を付ける「信用保証付き融資」を利用すれば、より大口の資金調達もしやすくなります。
審査では「継続的に受注が見込めるか」「返済能力があるか」が重視されるため、過去の実績や元請との契約書、見積書などを整え、自己資金をある程度用意しておくと通りやすくなります。
支店窓口や商工会議所の相談窓口でアドバイスを受けつつ、必要書類を準備して申し込みましょう。
- 一人親方でも家族を手伝わせられる?
-
一人親方でも家族を現場で手伝わせることは可能ですが、無償か有償かで手続きや保険・税務の扱いが変わります。
まず、家族が無報酬でサポートする場合は雇用契約や保険手続きは不要です。
ただし、事業に従事している事実があると税務上、家族従業者とみなされることがあるため注意が必要です。
一方、家族に報酬を支払う「有償従業者」とすると、労働保険や社会保険の加入義務が生じる場合があります。
加入要件は常時雇用人数や労働時間によって異なるため、労働基準監督署や年金事務所で確認することが大切です。
また、税務上は家族への給与を必要経費として認めてもらうには、実際に勤務した証拠として出勤簿などを整備し、業務との関連性を明確にしておく必要があります。
こうした対応を怠ると、経費として計上されなかったり保険未加入のリスクが生じるため、事前に専門家へ相談し適切な手続きをおすすめします。
