無料相談 24時間受付中
03-5579-9973
建設業を法人化するには?建設業許可との関係を解説
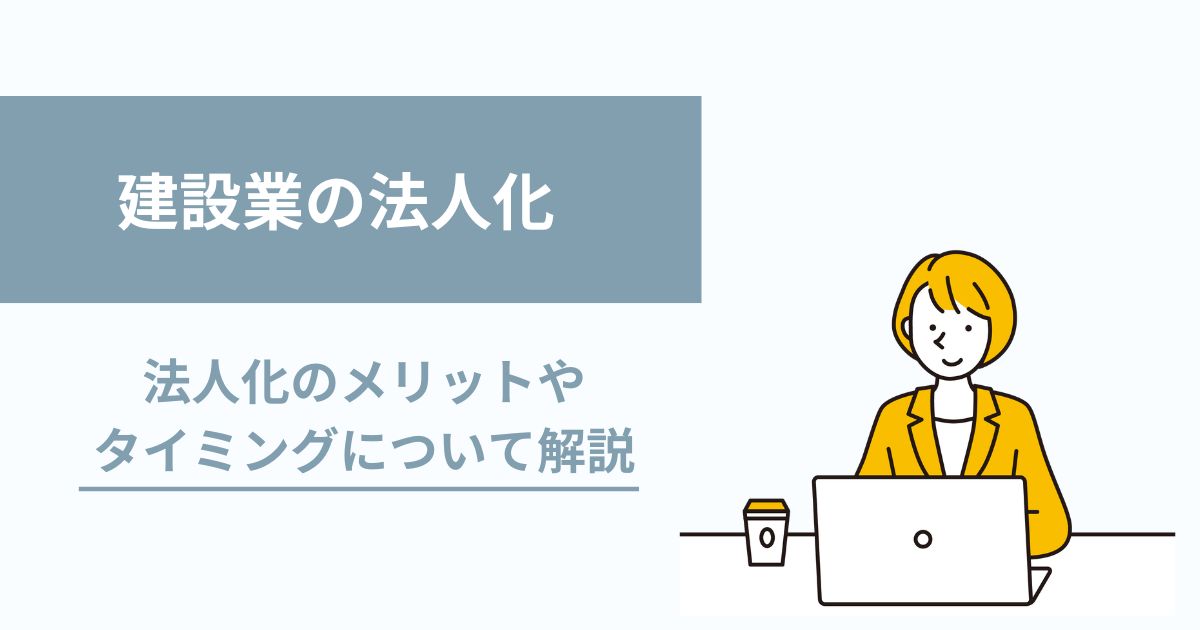
建設業を営むうえで「法人化」は、事業の信用力や成長の可能性を広げる手段の一つです。しかし、法人化を検討する際に気になるのが「建設業許可」との関係です。
個人事業主として取得している建設業許可は、法人設立と同時にどうなるのでしょうか。
今回は建設業を法人化する際に必ず押さえておきたい建設業許可との関係や注意点について詳しく解説します。
また、法人化の基本と手続きの流れについても併せて説明していきます。
建設業者の法人化とは?
建設業者の法人化とは、一人親方などが個人事業として営んできた建設業を株式会社や合同会社などの法人に形を変えて事業を継続することをいいます
法人化することで、事業の成長や信頼性の向上、契約の拡大、資金調達がしやすくなるなどさまざまな効果があります。
特に建設業界では、大型案件への対応や元請との取引の中で法人格が求められる場面も多く、法人化は業界内での地位向上や受注機会の拡大につながります。
ここからは建設業者が法人化を検討する際に押さえておきたい基礎知識や具体的なメリット・デメリット、手続きの流れなどについて詳しく説明していきましょう。
法人と個人事業主の違い
法人と個人事業主の主な違いは、「事業の形態」と「法律上の扱い」にあります。
一人親方などの個人事業主は、個人がそのまま事業を営む形式で、設立手続きが簡単で費用も少なく開業がしやすいのが特長です。
一方、法人(株式会社や合同会社など)は、事業と経営者が法的に別人格とされます。
税制面でも違いがあり、個人事業主は所得税が課せられ、法人は法人税が適用されます。
また、責任の範囲にも差があり、個人事業主は無限責任を負うのに対し、法人は原則として出資額の範囲内での有限責任となります。
事業の規模や将来の展望、社会的信用などを考慮して、自身に合った形態を選ぶことが重要です。
法人化のメリット
「もっと取引先の信頼を得たい」「事業を広げたい」と考える個人事業主の方にとって、法人化は有効な手段です。
法人化により会社の信用が高まり、資金調達や取引の幅が広がるなど、さまざまなメリットが生まれます。
次に法人化によって得られる代表的な3つのメリットを解説していきましょう。
- 信用力の向上
- 節税対策
- 人材確保
信用力の向上
法人になると、登記情報などが公開されるため、企業としての「見える化」が進み、取引先や金融機関からの信頼が高まります。
これにより、個人ではなかなか契約できなかった企業と取引ができるようになるなど取引のチャンスが増えたというケースも少なくありません。
また、法人名義で契約を結べることで、仕事の規模も広がりやすくなります。
ビジネスの可能性を広げたいなら、法人化を検討するのもよいでしょう。
節税対策
法人化は税金面でも有利になることがあります。
個人事業主のまま収入が増えると所得税が高くなりますが、法人化すれば法人税に切り替わり、節税ができるようになる場合があります。
また、経費にできる範囲が広くなったり、役員報酬を設定したり、家族に給与を支払って所得を分散させることも可能になります。
こうした仕組みを上手く活用することで、無理なく税金をコントロールしやすくなり、結果として手元に残るお金を増やすことも可能です。
人材確保
法人化することで、事業の引継ぎや人材採用にも強くなります。
法人は「会社」という形で存在するため、経営者が引退しても他の人が引き継ぐことができます。
これにより、親族や社員へのスムーズな事業の承継がしやすくなります。
また、就職先としても「法人」というだけで信頼感が生まれやすく、優秀な人材を採用しやすくなります。
福利厚生の整備や給与体系も明確になり、働く人にとっても安心感のある職場環境がつくりやすくなるのです。
法人化のデメリット
法人化にはさまざまなメリットがありますが、一方で見落とされがちなデメリットも存在します。
良い面だけに注目して法人化を進めてしまうと、後々思わぬ負担や手続きに悩まされることもあるのです。
次に法人化の代表的なデメリット、事前に知っておきたい注意点を説明していきましょう。
- 初期費用が掛かる
- 社会保険の加入
- 自由度が下がる
初期費用が掛かる
法人を設立するには、登記手数料や定款の認証費用などの初期費用がかかります。
さらに、法人を維持するためには、毎年の決算申告や法人住民税の均等割といった固定費が発生します。
個人事業主ならば比較的簡易な確定申告で済みますが、法人では専門的な会計処理が求められます。
税理士などの専門家に依頼するケースも増えるため、手間と費用の両面での負担が大きくなります。
また、事務手続きや書類の管理なども厳密さが求められ、経理や総務の体制が整っていないと対応が難しくなることもあります。
こうしたランニングコストと事務負担をしっかり見極めることが大切です。
社会保険の加入
法人になると、役員や従業員が1人でもいれば社会保険(健康保険と厚生年金)への加入が原則として義務化されます。
これにより、個人事業主時代には任意だった負担が固定費として毎月発生し、事業のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。
特に設立間もない小規模法人では、社会保険料が思った以上に経営を圧迫するケースもあります。
また、加入や変更、定期的な申請業務にも時間と手間がかかるため、慣れていないと対応に苦労するかもしれません。
法人化を検討する際は、社会保険に関する仕組みや費用についてもしっかり把握しておく必要があります。
自由度が下がる
法人は法律上、個人とは別の存在として扱われるため、経営者の自由な判断だけでは動かせない場面が出てきます。
たとえば、株式会社では株主総会や取締役会の承認が必要な事項があり、意思決定に時間がかかることもあります。
また、役員の報酬や契約内容なども明文化して管理しなければならず、個人の裁量で即座に動くのが難しくなるケースもあります。
加えて、法人の資金は「会社のお金」ですので、支出には厳しい制限がかかります。
自由に動きやすい個人事業主とは異なり、法人ならではのルールや責任を理解し、それに伴う制約も受け入れる必要があります。
建設業者が法人化すべきかどうかの判断
このまま個人事業で続けるべきか、それとも法人化すべきかと悩む場面は少なくありません。
法人化には、信用力の向上や節税の可能性、大型案件への参入など多くのメリットがある一方で、設立費用や社会保険の義務、手続きの複雑化といったデメリットも存在します。
そのため、法人化がすべての事業者にとって最適とは限りません。
建設業者が法人化を検討する際にチェックすべきポイントを確認しましょう。
一定の売上規模に達している場合
建設業者が法人化を検討する際に大きな判断材料となるのが売り上げの規模です。
一般的に、年間売上が1,000万円を超えてくると、法人化のメリットが現実的に見えてきます。
特に、消費税の課税事業者となるタイミングでは、法人の税制優遇や経費処理の柔軟性を活かすことで、節税効果が期待できるようになります。
また、取引先や金融機関からの評価も、売上が安定して一定規模に達している法人の方が信頼を得やすく、大型工事案件への参加や融資交渉もスムーズに進む傾向があります。
もちろん、法人化すれば維持コストや管理の手間が増えます。
しかしそれを上回るだけの事業的な体力が備わってきたと判断できる売り上げ水準に達しているのであれば、法人化を前向きに検討する時期だと言えるでしょう。
事業を拡大していきたい場合
建設業者が事業を拡大したいと考えるとき、法人化はおすすめです。
なぜなら、法人になることで社会的な信用力が高まり、元請会社や大手取引先からの信頼を得やすくなるためです。
これにより、これまで個人事業では難しかった大規模な案件や元請との直接契約にも挑戦できるようになります。
また、法人としての名義で融資を受けやすくなり、設備投資や人材採用に必要な資金を確保しやすくなる点も事業拡大には大きなメリットです。
さらに、従業員の福利厚生制度も整えやすくなり、優秀な人材を確保しやすくなるため、組織力の強化にもつながります。
個人事業主から法人化までの流れ
法人化には、会社の設立から建設業許可の再取得、税務・労務の届出まで、いくつかの重要な手続きがあります。
それぞれに必要な書類や手続きのルールがあり、順序を誤ると余計な手間や時間がかかることもあります。
しかし、ポイントを押さえて準備すればスムーズな法人設立と事業の引き継ぎが可能です。
次に個人事業主から法人に移行するための基本的な流れを紹介します。
法人化に必要な手続き
法人登記と建設業許可の手続きはできる限り並行して行うことがおすすめです。
法人設立後に許可申請すると、審査に数週間から1〜2か月かかる場合があるため、その間は許可を持たない状態になってしまう可能性があるからです。
特に公共工事や元請との取引が中心の事業者にとっては、無許可状態が業務に大きな支障をきたすおそれがあります。
そのため、事業承継制度の利用を含めて、法人設立のタイミングと許可申請の準備を事前に計画しておくことが重要です。
これらの手続きについての流れをみてみましょう。
基本事項を決定
法人化で最初にすべきことは、会社の「基本情報」を決めることです。
会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成などを明確にしていきます。
次に、株式会社であれば定款を作成し、公証役場で認証を受ける必要があります。
その後、設立に必要な資本金を会社名義の口座に払い込み、登記申請書類を法務局に提出し登記が完了すれば会社が正式に成立します。
手続きが複雑に感じる方は、行政書士や司法書士に依頼することで、スムーズに進めることも可能です。
市町村等への各種届出
会社が設立された後には、税務・労務に関する各種届出が必要となります。
まず、税務署には「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」などを提出し、法人としての課税関係を明確にします。
また、地方自治体(都道府県・市区町村)にも法人設立に伴う届出が必要で、法人住民税の納付などが発生します。
これらは設立から原則1〜2か月以内に行う必要があり、期限を過ぎるとペナルティが生じることもあるため注意が必要です。
きちんと届出を済ませることで、法人としての信頼性が整い、後の税務処理もスムーズになります。
許可に関する手続き
建設業を法人化する場合、個人事業主で取得していた建設業許可はそのまま使えないため、法人として新たに許可を取得する必要があります。
このとき、元の個人事業主と新設法人との関係性が明確である場合には、一定の条件のもとで「事業承継」として手続きが簡略化されるケースもあります。
ただし、いずれにしても人的要件を満たす必要があるため建設業許可要件を確認しておくことが大切です。
法人化を検討した時期から早めに専門家や役所に相談しておくとよいでしょう。
申請は都道府県庁や地域の建設業課を通じて行い、審査には数週間かかることもあります。
法人化後の事業継続に支障をきたさないよう、計画的に進めることが成功のポイントです。
法人化すべきタイミング
法人化のタイミングは、事業の成長段階や将来の展望によって異なりますが、いくつかの目安があります。
まず、売上が一定の規模に達し消費税の課税事業者となる場合、法人税制の方が有利になるケースが増えてきます。
また、大手企業との取引や入札など信用力が求められる場面が増えてきた場合も、法人化は検討すべき時期といえます。
さらに、従業員を雇い始めた、外部からの資金調達を考えている、事業を次の世代に引き継ぎたいといった状況でも、法人化によって組織の体制や継続性を強化できます。
法人化にはコストや手間も伴いますが、それを補える経営状況になったときがまさに法人化すべき時といえるでしょう。
建設業許可と法人化の関係
建設業を営んでいる事業者が法人化を検討する際に、特に注意が必要なのが建設業許可との関係です。
個人事業としてすでに建設業許可を取得している場合でも、法人化したからといってその許可がそのまま使えるわけではありません。
原則として、法人化と並行して建設業許可取得の準備をする必要があり、手続きのタイミングや方法を誤ると、業務が一時的に行えなくなるリスクもあります。
また、新たに法人で許可を取る場合には、建設業許可要件が再度問われるため、事前準備も重要になります。
では詳しく見ていきましょう。
法人化における建設業許可の扱い
建設業者が法人化を進める際に大事な点が、建設業許可の取り扱いについてです。
個人事業としてすでに建設業許可を取得している場合でも、法人化後にそのまま使用することはできません。
なぜなら、建設業許可は「事業者単位」で付与されるため、個人と法人は別の事業主体とみなされ、法人名義で新たに許可を取得する必要があるからです。
ただし、個人事業から法人へ事業を引き継ぐ形であれば、「事業承継」として一部要件が緩和されるケースもあります。
事業承継と似た言葉で「事業譲渡」がありますが、事業譲渡は他者に事業を売ることであり、建設業許可そのものについては事業譲渡ができません。
許可の再取得には、再度「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」や「営業所等技術者(専任技術者)」といった要件を満たす必要があります。
法人化と許可手続きは並行して準備を進め、法人設立後すぐに許可申請することで、空白期間なくスムーズに移行ができます。
法人化した際の許可の手続き
個人事業主の建設業許可を廃業している場合は、この後は通常の建設業許可の新規申請をします。
個人事業主と法人の代表者が同一で、かつ営業内容や体制が継続される場合には「事業承継」としての取扱いを受けられる可能性があります。
この場合、一部書類提出が簡素化され、人的要件が満たされていると判断されることもあります。
ただし、都道府県によって判断基準が異なるため、必ず事前に相談しましょう。
また許可の承継は承継の日から30日以内に申請する必要があります。
この期間を過ぎてしまうと承継扱いができず、新規許可の取得が必要になるため、スケジュール管理が非常に重要です。
必要書類をそろえて、法人本店所在地の都道府県建設業許可窓口に申請をします。
提出後、都道府県による審査となりますが、不備があるとさらに期間が延びるため、余裕をもったスケジュール設定が重要です。
許可が下りたら、建設業許可通知書が交付され、法人名義での営業が正式に可能となります。
この他、税務署や労働基準監督署などへの届出も忘れずに行いましょう。
建設業者の法人化におけるよくある質問
建設業者の法人化には「許可は引き継げるのか?」「どんな手続きが必要なの?」などわからない点が多いのも特徴です。
特に法人化の手続きは一度限りの経験になるケースが多いため、事前に正確な情報を知っておくことがスムーズな事業継続に欠かせません。
ここではよくある質問をまとめてみました。
- 法人化すると税金は安くなるの?
-
収入の規模や経費の使い方によっては、法人化によって税金の負担が軽くなる可能性があります。
ただし、すべてのケースで必ず安くなるわけではないため注意が必要です。
個人事業主の場合、所得税は累進課税制度が適用され、所得が増えるほど税率も上がります。
一方、法人の場合は法人税率が一定であるため、年間の所得がある程度以上になると法人の場合税率が低くなる傾向にあります。
また、法人化することで「役員報酬」「退職金」などの制度を使えるようになり、税金対策の幅が広がります。
さらに、法人では経費として認められる範囲も広く節税効果を得やすいのも特徴です。
ただし、法人になると法人住民税の「均等割」など利益が出ていなくても発生する税金があり、税理士費用や事務コストなども増える可能性があります。
- 個人事業の資産や契約はそのまま引き継がれるの?
-
個人事業の資産や契約は法人化によって自動的に法人に引き継がれるわけではありません。
所有している重機や車両、事務所などの資産は、法人に譲渡する手続きを踏む必要があります。
このとき、資産を法人の帳簿に計上するための仕訳や税務処理も発生します。
また、リース契約や業務委託契約、下請契約なども、契約先との合意のもとで法人名義に変更する必要があります。
これを怠ると、契約主体が違うと判断され契約無効になる可能性もあります。
建設業許可の事業承継制度を利用する場合には、資産や契約、従業員などが個人事業主時代と実質的に継続している必要があります。
- 社会保険や労働保険の手続きはどうなるの?
-
法人は法律上の事業体とみなされるため、たとえ社長ひとりの会社であっても、社会保険への加入が原則義務となります。
法人設立後は速やかに年金事務所へ届出をし、「新規適用届」「被保険者資格取得届」などの必要書類を提出します。
この手続きを怠ると、後からさかのぼって保険料を請求されるケースもあるため注意が必要です。
また、従業員を雇う場合には労働保険にも加入しなければなりません。
労災保険については労働基準監督署、雇用保険についてはハローワークに「労働保険成立届」や「被保険者資格取得届」を提出します。
労災については、経営者本人も条件を満たせば「特別加入制度」により補償を受けられることがあります。
これらの手続きは法人設立後できるだけ早めに行う必要があり、それぞれ提出先や必要書類も異なるため、あらかじめ準備しておくことが大切です。
